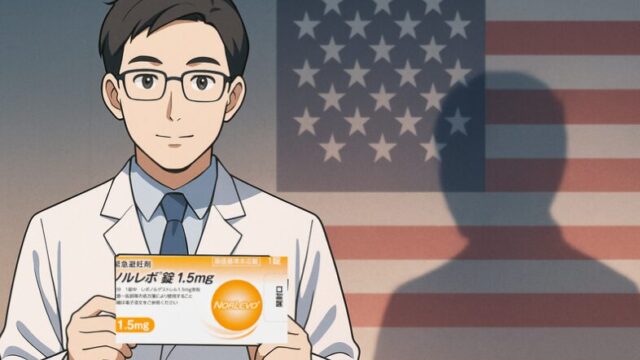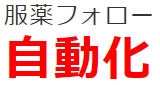散骨でいい、と言った人の話

彼は、薬局の待合いのいちばん端に座っていた。
壁と観葉植物のあいだの、視線が交わらない場所。
番号札を、指でひっくり返す。
表と裏を、意味もなく、何度も。
女性薬剤師に名前を呼ばれたとき、彼は一瞬、立ち止まった。
「〇〇 テツ 様」
はっとした。
テツは、奥さんがつけたニックネームだったようだ。
本当の名前は、哲(さとし)。
「嫁さんが昔からそう呼んでたから、読み間違いは慣れっこだよ」
たまたま、読み間違えただけだと、頭ではわかっている。
それでも、その呼び方を聞いた瞬間、彼の中で、家の中で呼ばれていた声だけが、急に戻ってきたのだと思う。
キッチンの向こうから、少しだけ笑いを含んだ声で、「テツ」と呼ばれる、あの音。
カウンターの前に立ちながら、彼は、自分が今いる時間が、数年前のものに感じたみたいだ。
数か月前からメンタル系の処方薬を受け取りに来るようになった患者さん。
薬の説明が始まるよりも先に、彼は言った。
「……俺、もう、どうなってもいいんです」
声は、驚くほど静かだった。
泣いてもいない。
怒ってもいない。
感情の出口だけが、ふさがっているみたいな音だった。
「葬式も、いらない」
「お墓も、いらない」
「散骨でいいです。海でも、山でも。誰も来なくていい」
“誰も”という言葉が、
最後に、少しだけ遅れて落ちた。
彼には、家族がいた。
妻と、子どもがひとり。
信号待ちの交差点で、後ろから来た車に、まとめて押し流された。
地元のニュースでは、「即死でした」と言ってたと思う。
まさかそのニュースの当事者の方が来るとは思ってもいませんでした。
即死。
痛みがなかった、という意味の言葉。
残された人の時間が、そこで止まる、という意味の言葉でもあった。
何回かお薬を渡しながら話を聞く機会があった。
葬儀は、ちゃんとやった。
黒い服を着て、頭を下げて、何度も、「ありがとうございました」と言った。
でも、棺が閉じた瞬間、彼の中で、何かも、一緒に閉じた。
それから、家は、“帰る場所”じゃなくなった。
冷蔵庫の中の牛乳は、誰のためでもなく、玄関にかかった縄跳びも、使う子供はいない。
夜、テレビをつけると、笑い声だけが、部屋に残る。
自分の声は、どこにも、跳ね返ってこなかった。
散骨の話をするとき、彼は、少しだけ視線を落とした。
「……あいつらは、ちゃんと、墓に入ってます」
「だから、俺だけでいいんです」
「適当に、風に流してもらえれば」
どういう事情か分からないが、自分だけ生き残ったことに何か後ろめたさを感じているようでした。
必要のない罪悪感で精神をむしばまれてしまっている気がした。
同じ場所に入ることすら、自分には、許されない気がしているみたいだった。
薬剤師は、励ませなかった。否定もしなかった。
代わりに、薬の袋を、両手で、彼の前に置いた。
「今日は、このお薬で……寝つきが良くなると思います」
「気にしていた悪夢も、少し和らぐとおもいます」
彼は、袋に印刷された文字を見る。
夢ですら、幸せだった過去を思い出させてくれないのかとおもうと、切なかった。
会計を終えて、ドアの前に立ったとき、彼は、外の光を見た。
夕方の、オレンジ色。道路の端まで、細く伸びている。
昔、この時間になると、
子どもが「ただいま!」と言って、走ってきた。
もう、来ない。
それでも、光だけは、今日も、同じように、そこにあった。
外に出ると、冷たい風が、コートの隙間から入り込む。
きっとこの寒さ、誰よりもこたえるんだろうな・・・。
その夜、私は、彼の言葉を、なぜか忘れられずにいた。
「散骨でいい」
あまりにも、軽く言われたその一言が、頭の中で、何度も、転がる。
ふと、本当に、どんなものなんだろうと思って、調べてみた。
出てきたのは、感情の話ではなく、段取りの話だった。
船を出す場所。
親族が立ち会えるかどうか。
代理で行ってもらう形もあること。
粉骨の工程。
終わったあとに、日時と場所を記した記録が残ること。
どれも、“消えるための方法”というより、残る人の生活を、できるだけ乱さないための仕組みに見えた。
そのとき、少しだけ、考え方が変わった。
散骨は、合理的な選択ではあるけれど、冷たい選択ではないのかもしれない。
自分の終わり方を、ここまで具体的に考えるということは、最後の最後まで、他人の時間の中に、自分を置いているということでもある。
全くの孤独ではなく、まだ彼には、彼のことを心配に思う人がいるんじゃないかなと思うと少しほっとした。
ふと思った。
それは、“消える”やり方じゃなくて、最後に、自分の生きざまを、世の中にそっと示すやり方なんじゃないか、と。
何も残さない、という形で。
誰かに、面倒をかけない、という姿勢で。
自然の中に、静かに戻る、という選び方で。
それもまた、ひとつの“生き方”なのかもしれない。
散骨を選ぶ人の中には、「忘れてほしい」のではなく、「自分のことで困らずに、生きてほしい」と願っている人がいる。
ただ、その願いは、残された人にとって、やさしさと同時に、行き場のない寂しさになることもある。
会いに行く場所が、なくなるから。
もし、散骨という選択を、物語ではなく、現実の選択肢として、そっと見てみたいと思ったなら。
海に還すという形を、段取りとして、静かに確認できる場所がある。
海洋散骨の流れと費用を確認する
そこに並んでいるのは、希望でも、哲学でもなく、当日の流れと、費用と、選べる形式だ。
家族で船に乗る形。
立ち会えない場合に、代わりに行ってもらう形。
終わったあとに、日時と場所を記した記録を受け取る形。
どれも、“消えるため”というより、残る人の生活を、できるだけ乱さないための設計に見える。
散骨は、合理的な選択のようでいて、とても、感情的な選択でもある。
やさしさと、諦めと、責任感と、静かな孤独が、同じ場所に並んでいる。
彼は、まだ、生きている。
理由があるからでもなく、希望が見えたからでもなく、
ただ、今日も、誰かが、彼とかかわり一生懸命生きているから。
それだけで。
散骨を考えること自体が、もうすでに、誰かの時間の中に、自分を置いている証拠なのかもしれない。
(当然のことですが、プライバシーに配慮して記載しています)